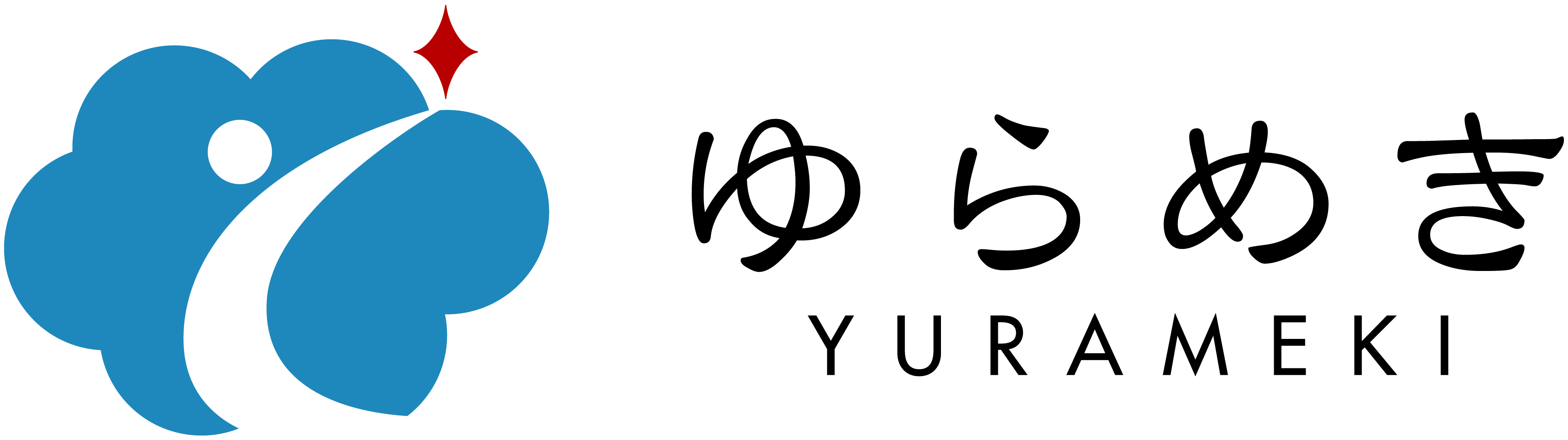2025年– date –
-

アスリートが学ぶもの
「2021年から英語が一定の基準に達しない選手は、代表に選ばない」 フェンシング協会が発表した。 理由は、 1.他国の選手や審判とコミュニケーションが取れる。 2.現役を終えた後(セカンドキャリア)にも、職業の選択が広がる。 現役を終えた後のこと... -

自分って、何者?
自分って? 女房から見れば、夫。 2人の娘たちから見れば、お父さん。 孫たちから見れば、おじいちゃん。 研修受講者さんから見れば、講師。 地域社会では、年配者。 ゴルファーから見れば、インストラクター。 行きつけのラーメン屋さんから見れば、 常連... -

マイナスがプラスに
水族館プロデューサーの 中村元(なかむらはじめ)さん。 魚への興味も知識も無い飼育員時代の 彼の体験談が面白い。 鳥羽水族館で 団体客に解説するサービスで、 アカウミガメとアオウミガメの違いを 説明するのだが、誰も聞いてくれない。 「『浦島太郎... -

責任を持った行動が少ない要因
コーチング研修で新たな課題が見つかった。 指導者の関りで、 責任の所在の割合を受講者(12名)に考えてもらった。 1.指導者からの『指示・指図』からの行動 2.求められていないのに意見を言う『忠告』からの行動 3.求められて意見を言う『アドバイ... -

モチベーションの高め方
モチベーションとは、感情・気持ち。 これは先立つ事はあるのか? ない。 感情は必ずアクション後に発生する。 そして、その成果が良かった後に モチベーションは上がる。 結果を出すには、どうしたらいいのか? アクションを起こすこと。 たくさん行動す... -

【成功と失敗、あなたはどっちがいい?】
成功と失敗。 成功した後に言われる言葉。 「勝って兜の緒を締めよ」 失敗した後に言われる言葉。 「失敗は成功のもと」 成功後は、戒められ、 失敗後は、励まされる。 どちらが人の成長に 効果的なんだろう? スポーツで例えるなら 勝利で得られるもの。 ... -

失敗と改善の関係
挑戦とは、 成功するか失敗するかではなく、 改善するか、改善しないかである。 これからの世の中は、 正解がわからない時代となる。 コロナが今後どうなるか、 誰もわからない、と言うように。 「失敗するかも」という思考が、 挑戦にストップをかける。 ... -

主体性とコミュニケーションの関係
愛媛県立長浜高校の 『水族館部』 ここでの活動で生徒が発表した論文が、 国際的な評価を受けた。 顧問の先生は、 生物の教師だが、 専門家ではない。 先生は、 「研究の方向性を示しはするが、実際にテーマを決めて行動するのは生徒に任せている」 「私の... -

脳をだます表情フィードバック
能動的にせよ受動的にせよ、 「笑顔」を作ることは、 良い感情を引き起こすことにつながる。 笑顔になれば、 他人に好印象を与えるだけでなく、 自分自身も楽しく感じられる。 誰もがにこやかな家庭は、 幸せが倍増するであろうし、 スポーツクラブでも 指... -

人の成長の妨げとなるもの
「教えない指導」 その重要性が日に日に強くなってくる。 自分の実行(パフォーマンス)を 頭で理解できないと、 言葉にはできない。 頭で理解できないことは、 身体でも表現できない。 頭で理解するには、 想像(イメージ)が不可欠。 イメージできなけれ...