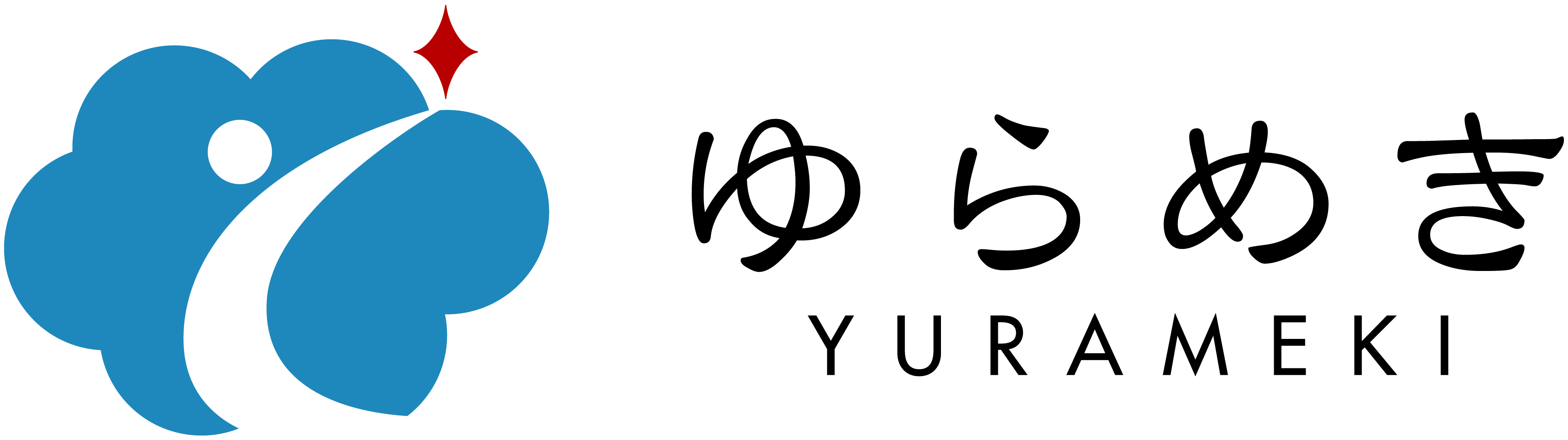2025年– date –
-

何が必要か? なら、どうすればいい?
「知性と技術だけでは、世界の幸せに繋がらない」 「知性」・「スキル」・「ハート(思いやり)」 思いやりを育む理由。 腕のいいスリは頭がよく、 高いスキルを持っている。 他人の痛みを感じる共感性を持ち、 助け合って人々の問題を 解決する優しい心を... -

子どもの効果的なスポーツ指導の重要性
女子スピードスケート選手だった、 小平奈緒さんは言った。 「達成できる人は、競技においては一人だけ」 「達成するために最善を尽くすことは、誰もができる」 欲しくてたまらないものを 手に入れられるかどうかより、 手に入れるために ベストを尽くす。... -

愛が付くものと、付かないものの違いは?
「愛車」 機械に対して愛がつくものは、 車だけのように思う。 なぜ? 洗濯機、冷蔵庫には、付かない。 愛がつくもの。 愛妻、愛犬、愛娘(まなむすめ)、愛息。 何が違いを生み出しているんだろう? 「動きの有無」 動くものに対しては、 「愛」がついて... -

生きがい
脳科学者の茂木健一郎氏は、 人生100年時代を 幸せに生きるキーワードとして、 「生きがい」を挙げる。 生きがいとは、 「生きる喜び」「人生の意味」 を指す言葉。 仕事や研究など 専門領域で成功をおさめなくても、 楽しみながら見いだせる目的。 成功を... -

選手が意識するモノと言葉の関係
スポーツの秋。 色々なスポーツ大会が開催されだした。 そんな中、優勝者のインタビューで、 気付きがあった。 話の内容が、2つの種類に別れた。 1つは、プレッシャーを感じながら、 頑張ったという内容。 もう1つは、自分がすべきことが、 できたか、で... -

表現と感情の関係
人が落ち込んだ時の姿の特徴 目線は、下を向いている。 姿勢は、背中が丸くなっている。 顔つきは、どんよりしている。 感情が姿勢を作り、行動を作る。 ならば、 姿勢や行動が、 感情を創り出すことも可能かもしれない。 気分がいい時と良くない時の 「視... -

変えるのではなく、気づいてもらう
他人は、なかなか変えられない。 指導者が研修を受け入れない現状がある。 特に子どもの指導者は、 専門の指導知識、 スキルが無くても指導ができる現状。 子どもは反論しない。 保護者は、 スポーツ指導に関して素人だから 意見は言わない。 自分の指導が... -

もう一つのゴール
今回の大会は調子も良く、 ベスト8をゴールとしていたが、 結果は、9位となった。 その要因を考えた時、 ゴールをベスト8ではなく、 7位にしておいた方が、 結果として8位になれたのかもしれないという 意見が出た。 そんな話を聴いた時、 人はゴール直前... -

言い訳や自分を卑下する言葉の意味
色々な人とゴルフをプレーして、 気づいたことの一つに 言い訳をする人や 自分のプレーを卑下する人の多いこと。 さらにそのような言葉を発した人に対して、 同伴者は言う。 「ドンマイ」とか、 条件が良くなかったことを言ってフォローする言葉、 「今の... -

誰から学ぶか?
他者から学ぶとき、 誰から学ぶのがいいか? プレーヤー同士で学び合う時、 誰と一緒にプレーすることが学びをもたらすか? 技術を学ぶときは、 自分よりも上手なプレーヤーが効果的である。 自分よりも技術が未熟なプレーヤーは、 何ももたらさないのだろ...