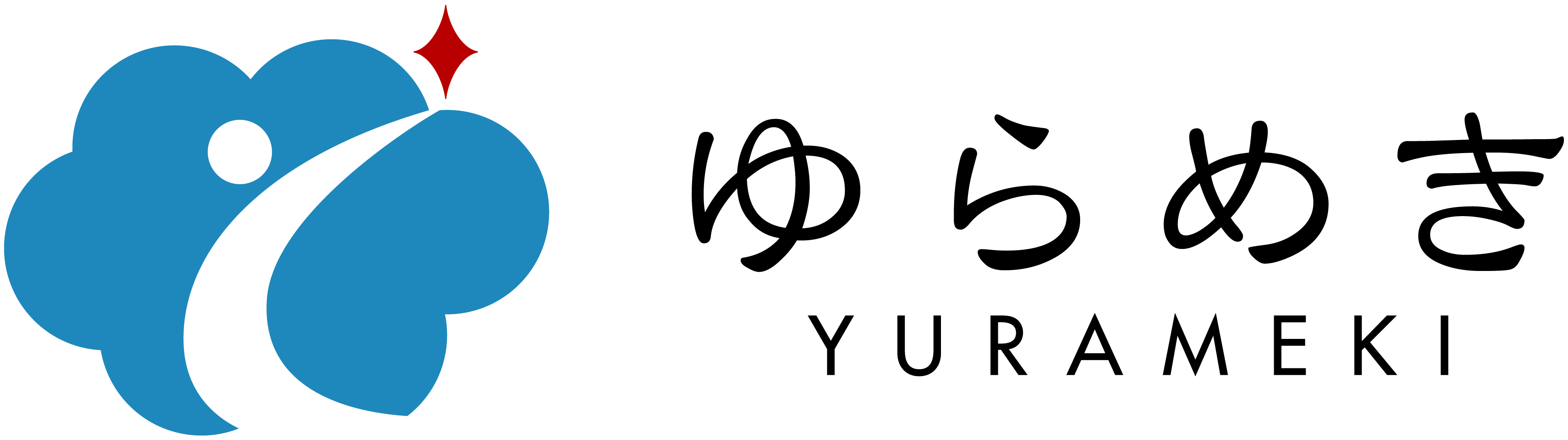「目的」が不明確な未来って?
テクノロジーの教育活用に詳しい
デジタルハリウッド大学大学院の
佐藤昌宏(さとうまさひろ)教授は言う。
「日本では小学校で2020年度からプログラミング教育が必修化されたように、プログラミングだけが独立している。海外では、『プログラミング教育』という教科はない。米国は『コンピューター・サイエンス』、英国なら『コンピューティング』という教科があり、その中の1つとして『プログラミング』がある」
「コンピューターはなぜ動くのか、インターネットはどうつながっているのか、といった全体像を学ばずにプログラミングという細目に特化すると、生徒や学生は『つまらない』『難しい』となりがちだ。ましてや、キーボードも打てない大学生も多い。数学が苦手だから文系に進んだのに、なぜ計算式や統計をやらなくてはいけないのかと、IT嫌いを増やしかねない」
この発言内容には、
今後のプログラミング教育を実践するうえで
重要な事柄が詰まっている。
仕組みを理解し、
情報を深め、
価値を見いだす。
そして、手段・方法に移行する。
最初から手段・方法に取り組み、
「目的」が不明確で
テクニックだけ備えた人の未来、
イメージしてください。
何のためにスポーツを行っているのかという
「目的」が不明確な
強靭な体力、
高度な技術を備えたスポーツ選手。
どんな未来が待っているんだろう?